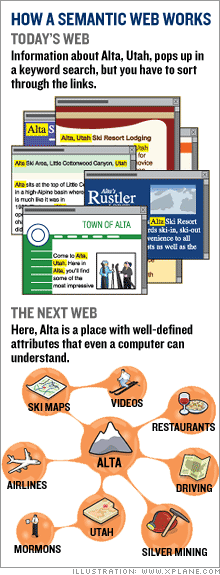何かを調べるときは、いつもGoogleを使う。自分が知りたいものはほとんどWebにある。今、書こうとしているセマンティック・ウェブに関しても、数時間前は知識ゼロだったが、今やWeb2.0からの流れ、業界地図、市場規模までわかる。
セマンティック・ウェブとは、Webサイトが持つ意味をコンピュータに理解させ、コンピュータどうしで処理を行なわせるための技術のことである。
例えば、スキーに行くとする。
現在のWeb検索では、どこに行くか、どうやって行くか、どこに泊まるか、天気はどうか、積雪はどうかなど、それぞれ「個別に」調べなければならない。「るるぶ」や「Googleマップ」、「ウェザーニュース」など、何個もサイトを訪れて、やっと情報を集めることができる。何せ、Webには全て情報が載っているから、これでも事足りるが、もっとユーザビリティを高めることができるはずだ。これを実現させるのが、セマンティック・ウェブである。
セマンティック・ウェブでは、スキーの行先候補の「白馬」と選択しただけで、行き方、近くのホテル、その価格帯、写真、動画、ユーザからのコメント(まだ積雪が少ない、等)、お勧めのお土産、等々が一覧で出てくる。
技術的な話をすれば、セマンティック・ウェブで用いられえるのは、XMLをベースとしたメタデータであり、コンピュータはこれをもとに、Webサイトの情報を理解する。このメタデータを記述するためのフレームワークが「RDF」(Resource Description Framework)であり、このRDFによってタグ付けされたメタデータがコンピュータの解釈を可能にし、情報の自動的に整理・処理することを可能にする。
これによって、全てのWeb上のデータは、「a series of connected databases, where all information resides in a structured form.」(WWWの創始者ティム・バーナーズ・リー)になる。
セマンティック・ウェブの市場規模は現在、70億ドルに過ぎないが、2010年には、500億ドルにまでなるとされる。
検索業界の王様、Googleの時価総額はトヨタを抜き、起業から10年程度しか経っていないこの企業に、全ての日本企業は追い抜かれてしまった。
しかし、逆を言えば、インターネットの世界の肝である「検索」業界においては、Googleを抜く企業が出て来得るということだ。Google、Yahoo!、MSNが提示する結果は、その内容においては画一的であり、インターフェースにおいては、サービス開始当初からほとんど何も変わっておらず、原始的なままだ。それは、あまりに慣れ親しんでしまったため、不満を一切感じないほどでもある。
この分野のベンチャーでは、Garlik、Metaweb Technologies、Powerset、ZoomInfoなどが注目されている。
だれがGoogleを超えるか?